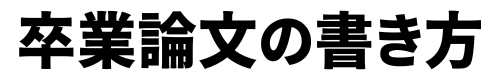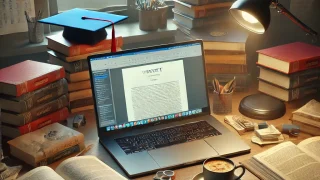「卒業論文を提出したのに、まさかの不合格…」そんな悩みを抱えている方も多いのではないでしょうか。
卒論が不合格になると、留年してしまう可能性もあります。
本記事では、なぜ卒論が不合格になり卒業できなくなるのか、具体的な理由や避けるべきポイントについてわかりやすく解説します。
卒業論文が不合格になる基準とは?
卒業論文が不合格になる基準は、大学によって異なるものの、共通して注意が必要なポイントがいくつかあります。
「頑張って書いたのに、不合格だったらどうしよう…」と心配する方もいるかもしれませんが、事前に基準を理解し、ミスを防ぐことで、不合格リスクを大幅に減らすことができます。
この章では、卒論が不合格となる主な理由をわかりやすく解説します。
提出期限内に卒論を提出しない
卒業論文は、決められた提出期限内に必ず提出しなければなりません。
提出期限を守らないと、内容に関係なく「不合格」や「未提出」として扱われ、卒業が難しくなることがあります。
提出期限が厳守される理由には、大学側がすべての論文を公平に評価するための時間を確保することが挙げられます。
そのため、たとえ書き上げたとしても期限を過ぎてしまうと、不合格になってしまうのです。
厳しいところだと提出期限を1分でも超えると受け取ってもらえないこともあるそうです。
・提出期限に遅れる原因と対策
提出期限を守れない原因には、以下のようなことが考えられます。
- 計画の遅れ:書き始めが遅く、終盤で慌ててしまい、期限に間に合わないケース
- 予期しないトラブル:体調不良やパソコンの故障など、予測できない問題が発生する
- 手続きの確認不足:必要な書類やフォーマットに気づかず、提出直前に慌ててしまう
こうしたトラブルを避けるために、提出までの計画をしっかり立てることが大切です。
例えば、締め切りの1週間前までに完成させる、予備日を設けるなどの対策をすると、予期せぬ事態にも余裕を持って対応できるでしょう。

既定のルールを守られていない
卒業論文には、大学ごとに決められたルールやフォーマットがあり、それらを守ることが求められます。
ルールを守らないと、内容が良くても「不合格」とされることがあるため、事前にしっかり確認しておくことが大切です。
以下は、よくあるルール違反の例と対策です。
・よくあるルール違反の例
- 形式的な違反:文字サイズや行間、ページ数など、指定されたフォーマットを守らない。
- 引用ルールの無視:他の論文や資料を引用する際に、出典を正確に記載していない。
- 指定の提出形式でない:紙での提出が求められているのにデータで提出してしまう、またはその逆。
- セクション構成の不備:序論・本論・結論など、構成が指定されているにもかかわらず、必要な項目が欠けている。
大学が配布する卒論のガイドラインを一通り確認し、ルールを守っているのかをチェックしておきましょう。
ルールを守ることは、論文の質と同じくらい大切です。
ルール違反を防ぐための準備を怠らないようにしましょう。
剽窃(他論文のコピペ)の発覚
卒業論文では、他人の研究や文章を無断で使う「剽窃(ひょうせつ)」が厳しく禁止されています。
剽窃が発覚すると、ほとんどの場合、不合格になります。
剽窃とは、他の論文やウェブサイトからのコピペや、出典を示さずに他人の意見やデータを自分のものとして使う行為を指します。
・具体例としての剽窃行為
- コピペそのままの使用:他の論文や書籍の文章をそのまま自分の論文に使ってしまう。
- 出典不明な引用:参考にした情報があるのに、出典を記載しないで使ってしまう。
- 翻訳の無断使用:外国語の論文を自分で翻訳した場合でも、出典がなければ剽窃とされることがある。
剽窃を避けて誠実な論文を書くことは、学問に対する姿勢としても重要です。
出典の記載やオリジナリティを守り、不合格にならないように心がけましょう。

口頭試問での受け答えが全然できていない
卒業論文の提出後には「口頭試問」と呼ばれる質問や確認の場が設けられることが多くあります。
これは、教員が論文の内容を理解しているか、また研究の意図や過程についてしっかりと説明できるかを確認する場です。
口頭試問でうまく受け答えができないと、論文自体が評価されにくくなり、不合格になることもあります。
・受け答えがうまくいかない例
- 論文のテーマや目的が明確に説明できない:何を研究したのか、なぜそのテーマを選んだのかをはっきり答えられない。
- 重要な用語や理論を理解していない:自分で使った用語や理論の意味を聞かれても答えられないと、理解が浅いと思われる。
- 実験や調査の結果について説明できない:結果のデータやグラフについて質問されたときに、具体的な内容や分析の意図を答えられない。
口頭試問での受け答えは、論文をしっかり理解していることをアピールする大切な機会です。
質問に的確に答えることで、合格への道が開かれます。

卒論の質が低すぎる
卒業論文が不合格になる理由として「論文の質が低すぎる」ことが挙げられます。
論文の質が低いと、研究としての価値が認められず、評価されにくくなります。
質が低いと判断されるのは、単に文章の書き方だけでなく、内容の浅さや分析の不十分さ、論理的な一貫性が欠けている場合です。
以下に具体例を挙げながら説明します。
・質が低いとされる例
- 調査や実験が不十分:調査データが少なすぎたり、実験が簡単すぎて十分な検証ができていない場合、論文の信頼性が低くなります。
- 分析や考察が浅い:ただデータを並べただけで、結果の意味や理由を深く考察していないと、読み手に伝わるものが少なくなります。
- 論理が飛躍している:結論に至るまでの論理のつながりが弱いと、論文全体がまとまりのない印象を与え、説得力が欠けます。
- 文法ミスや誤字脱字が多い:基本的な誤字や脱字が多いと、読みにくくなり、完成度の低さが目立ってしまいます。
質の高い論文を書くには、研究内容の充実とわかりやすさの両方が大切です。
内容に説得力を持たせるためにも、しっかりと準備をして臨みましょう。

卒業論文が不合格になる基準のまとめ
卒業論文が不合格になる主な理由として、提出期限を守らない、既定のルールを守らない、他論文の剽窃、口頭試問での不十分な受け答え、論文の質が低すぎることが挙げられます。
これらの基準を満たさないと、不合格や留年につながる可能性が高まります。
不合格を避けるためには、提出期限や形式を守り、剽窃を避けた上で質の高い内容にすることが重要です。
また、口頭試問への準備も怠らず、自分の研究をしっかり説明できるようにしましょう。